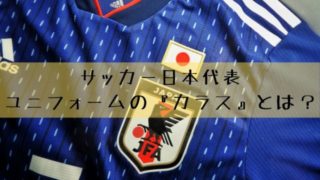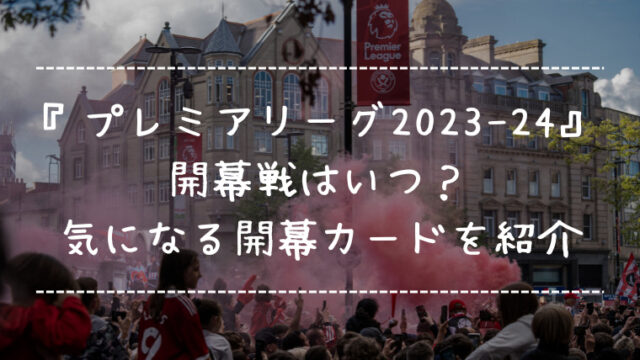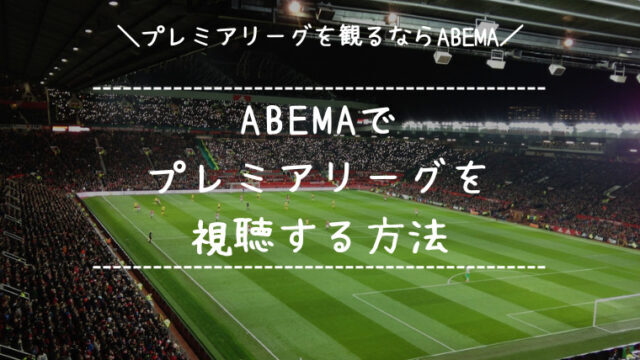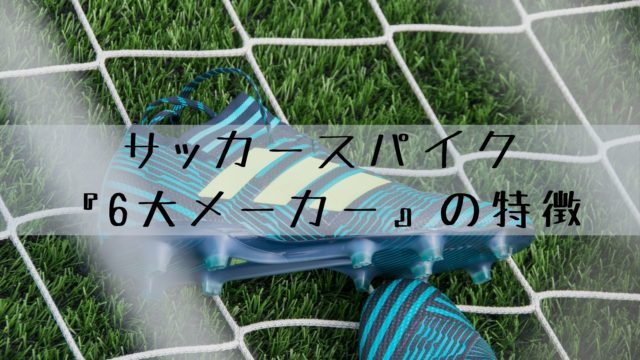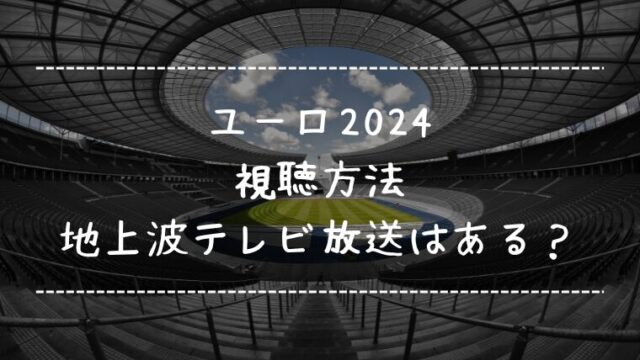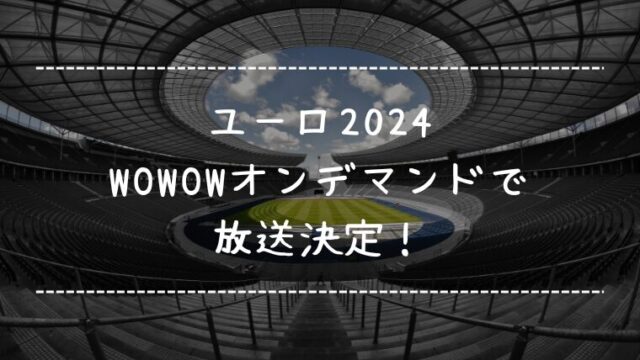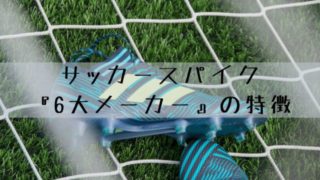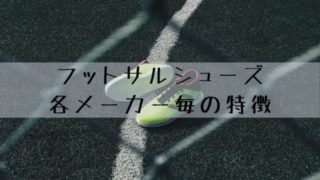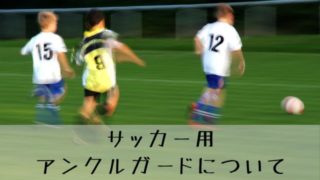- サッカー日本代表が「サムライブルー」って呼ばれるのはどうして?
- いつから「サムライブルー」って呼ばれているの?
サッカー日本代表の試合をテレビで見ていると、『サムライブルー』という言葉をよく耳にします。
『サムライブルー』は男子サッカー日本代表の〝愛称〟なのですが、なぜサムライブルーと呼ばれているのかわからない方も多いことでしょう。
そこで本記事では、サッカー日本代表が『サムライブルー』と呼ばれる起源や由来、込められた想いについて紹介します。
- サッカー日本代表がサムライブルーと呼ばれる意味を知りたい人
- サッカー日本代表がサムライブルーと呼ばれる由来を知りたい人
- サッカー日本代表のカラーが青色の理由を知りたい人
\ワールドカップを観るなら『ABEMA』がおすすめ/
本田圭佑の解説が面白い!
サムライブルーの起源〝ブルー(青色)〟とは
女子サッカーが『なでしこジャパン』と呼ばれるように、男子サッカーにも愛称があって『サムライブルー(SAMURAI BLUE)』と呼ばれています。
サムライブルーの〝ブルー〟について、なぜサッカー日本代表のカラーは青色になったのか、サムライブルーの起源を見ていきましょう。
サムライブルーの由来(なぜ青色なのか)
「日本の国土を象徴する海と空の青」と一般的に考えられていますが、実際は後になってつけられた理由で、なぜ青なのかということは文献が残っておらず不明です。
日本のユニフォームは、戦前に水色を採用しており、戦後もそれが引き継がれていました。
1964年の東京オリンピックでは上下とも白となり、メキシコオリンピックでは白のユニフォーム+紺色のパンツが使用されました。これ以降は白と紺色が基調となっています。
1988年以降に赤と白のユニフォームが採用された時期がありましたが、1992年には再び白と青のユニフォームに戻りました。それ以降は青と白を採用しており、現在のSAMURAI BLUEに象徴されるように青を使用しています。
日本サッカー協会オフィシャルサイト
日本サッカー協会が述べているように、サムライブルーがなぜ〝ブルー(青色)〟なのかということは文献が残っていないために〝不明〟なようです。
わかっていることは、戦前から水色のユニフォームを着用していて、それが現代まで続いているということのみになります。
『日本=青色』という理由は後付けのようですね。
『日本の海と空の青』をイメージした説
日本サッカー協会にも記述されているように、『日本の国土を象徴する海と空の青』をイメージしたものではないかと、一般的には考えられています。
日本という国は周囲を海で囲まれているので、
- 日本国民がわかりやすいように
- 世界各国の人がイメージしやすいように
後付けされたのでしょう。
『縁起がいい』という説
1936年(昭和11年)のベルリンオリンピックで、日本代表は優勝候補だったスウェーデン代表を破りました。
これは『ベルリンの奇跡』と呼ばれているそうで、その時着用していたユニフォームが〝青色〟だったということで、縁起がいいため日本代表に青色が定着したともいわれています。
アトランタオリンピックでブラジル代表を破る『マイアミの奇跡』でも青色のユニフォームを着用しています。
『強かった大学が着用』していた説
まだプロが無い時代の話までさかのぼるのですが、その時代はクラブチームと同じくらい大学のチームが強かったそうです。
日本サッカー初期の頃に強かったのが東京大学のチームで、そのチームがライトブルーのユニフォームを着用していたことから青色のユニフォームという説もあります。
願掛けみたいなものでユニフォームの色を決めたのでしょうか。
『欧米人がジャパンブルーと名付けた』説
日本の国旗だけを見ると、日本=赤というイメージがありますが、なぜ青色が日本を象徴する色になったのでしょうか。
明治期に来日した欧米人が、〝藍〟を染料とした青色が多いことが印象的で、街中に溢れる「藍色の美しさに驚いた」ことから藍染めを〝ジャパンブルー〟と称賛したとも言われています。
のれんや着物などの〝藍色〟に魅了され、海外では『藍染めの青色=日本』というイメージがあるのでしょう。
現代でも藍染めは海外の方から人気ですね。
サムライブルーの由来と込められた思い

サッカー日本代表のカラーであるブルー(青色)の由来は不明で、後付けで理由をつけられているとわかりました。
では、どのように『サムライブルー』という愛称ができたのか、込められた意味はあるのか紹介します。
サムライブルーの由来
日本代表の愛称です。2006年、日本代表がFIFAワールドカップドイツ大会に臨むにあたり、「2006日本代表キャッチフレーズ」として命名されたもので、ワードの選考にあたっては、「SAMURAI BLUE2006」、「Make the HISTORY」、「世界を驚かせよう」、「頂点へ、全員で。」、「WIN NOW!」の5つの案を策定し、サポーター投票を実施。その結果、「SAMURAI BLUE2006」が1位を獲得しました。
大会後、JFAはSAMURAI BLUEを日本代表チームの愛称として使用することを決め、以来、日本代表チームの愛称として使われています。
SAMURAI BLUE(日本代表)は、日本国籍を有する選手で構成される日本最高峰のチームで、FIFA(国際サッカー連盟)やAFC(アジアサッカー連盟)などが主催する国際大会での飛躍を目指しています。
チーム最大の目標は、FIFAワールドカップでの優勝。JFAは『JFA2005年宣言』で、2050年までに日本でFIFAワールドカップを開催し、その大会で日本が優勝する、ということを表明しています。
FIFAワールドカップには1998年のフランス大会に初出場して以来、2010年大会まで4大会連続で出場、2002年日韓大会と2010年南アフリカ大会でベスト16の成績を収めました。
日本サッカー協会オフィシャルサイト
『サムライブルー』は、2006年のワールドカップドイツ大会に挑む際に命名されたキャッチフレーズで、5つの案から『SAMURAI BLUE 2006』がサポーター投票で決定されたようですね。
大会後にも使用できるように、サッカー日本代表の愛称を『SAMURAI BLUE(サムライブルー)』に決定しました。
意外にも最近できた愛称だったようです。
監督が代わるたびに、監督の名前を使用して『○○ジャパン』(ザックジャパンや森保ジャパンなど)と呼ばれるので、サムライブルーはあまり使用されていないような気もします。
『サムライブルー』のように、各国の代表チームも愛称があって、
- フランス=レ・ブルー
- スペイン=ラ・ロハ、無敵艦隊
- イタリア=アズーリ
- ブラジル=カナリーニョ、カナリア軍団
- イングランド=スリーライオンズ
などと親しまれています。
このように強豪国の愛称は定着していますが、日本のサムライブルーは、まだまだ定着したとはいえませんよ。
監督がコロコロ代わるせいもあるかもしれませんが、国際大会で活躍することで『サムライブルー』が定着してくるといえるでしょう。
海外の解説で『サムライブルー』と呼んでもらいたいですね。
サムライブルーに込められた意味
サムライブルーの〝サムライ〟と〝ブルー(青色)〟には、どうやら深い関係があるようです。
日本の伝統工芸でもある藍染めで使用される、〝藍〟の色の中には、『褐色(かちいろ)』と呼ばれる色があります。
この褐色に染めた布を、侍が好んで身に付けていたと言われています。
藍色は深くて美しい色ですよね。
この藍色を侍が好んでいたのには以下のような理由があります。
- 藍色の中にある褐色(かちいろ)= 勝ち色 → 戦いに勝つ色
- 藍染めの中にある叩く(かつ)という工程 = 相手を叩いて勝つ
このように、藍染めの『褐(かつ)』を『勝つ』に読み替えて、侍が戦に勝利するための験担ぎとして使用されていたとされています。
サムライブルー=勝負に勝つための色
ということになるので、サッカー日本代表は『勝負に挑むための青色』を身にまとって戦っているサムライということになります。
藍色は戦いに勝つための色として縁起がいいとされているのでしょう。
\ワールドカップを観るなら『ABEMA』がおすすめ/
本田圭佑の解説が面白い!
サムライブルーは勝負に挑むサムライの青色|まとめ
『サムライブルー』とは、ドイツワールドカップに挑む日本代表のキャッチフレーズとして命名されたものです。
サッカー日本代表の青色のユニフォームの理由は後付けで諸説ありますが、たくさんの想いや期待、メッセージが込められているのがわかります。
日本代表のユニフォームを着用した選手たちには、その重みを感じながら、誇りと〝サムライ魂〟を持って闘ってもらいたいですね。
サッカー日本代表のこれからの活躍にも期待です。
\サッカー日本代表のエンブレムに描かれたカラスの正体と意味はコチラ/